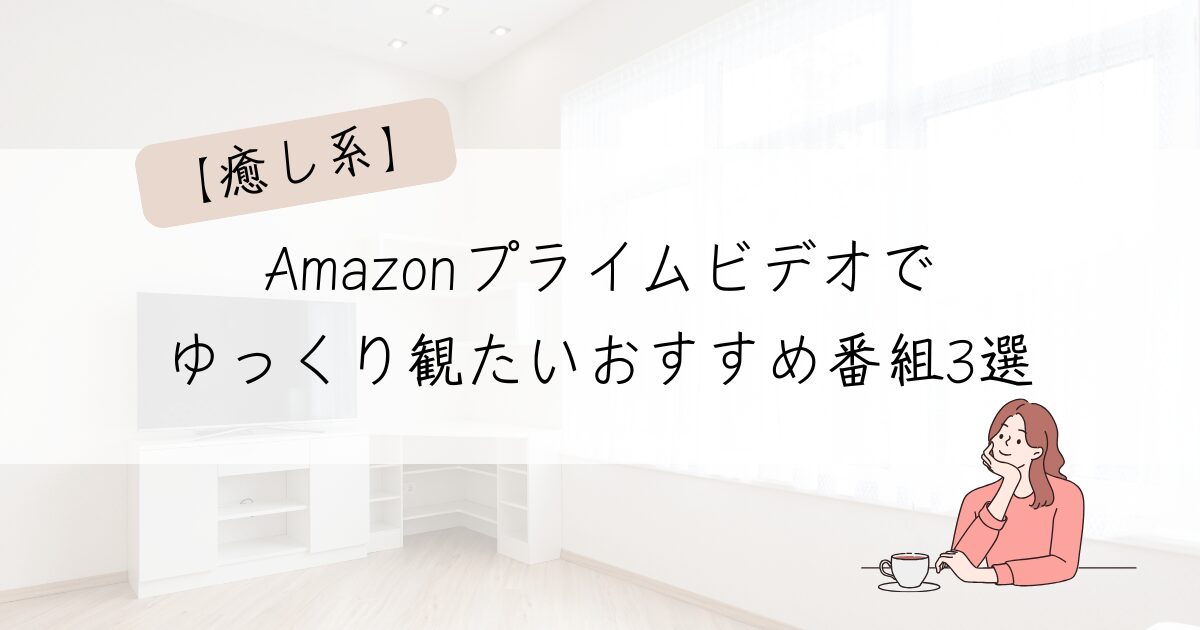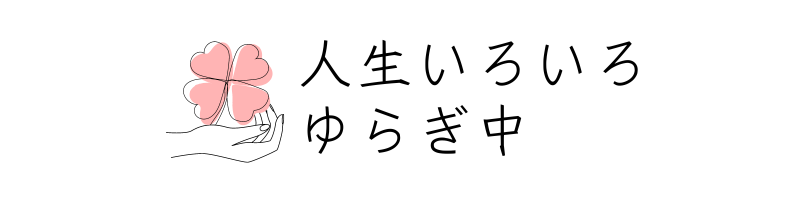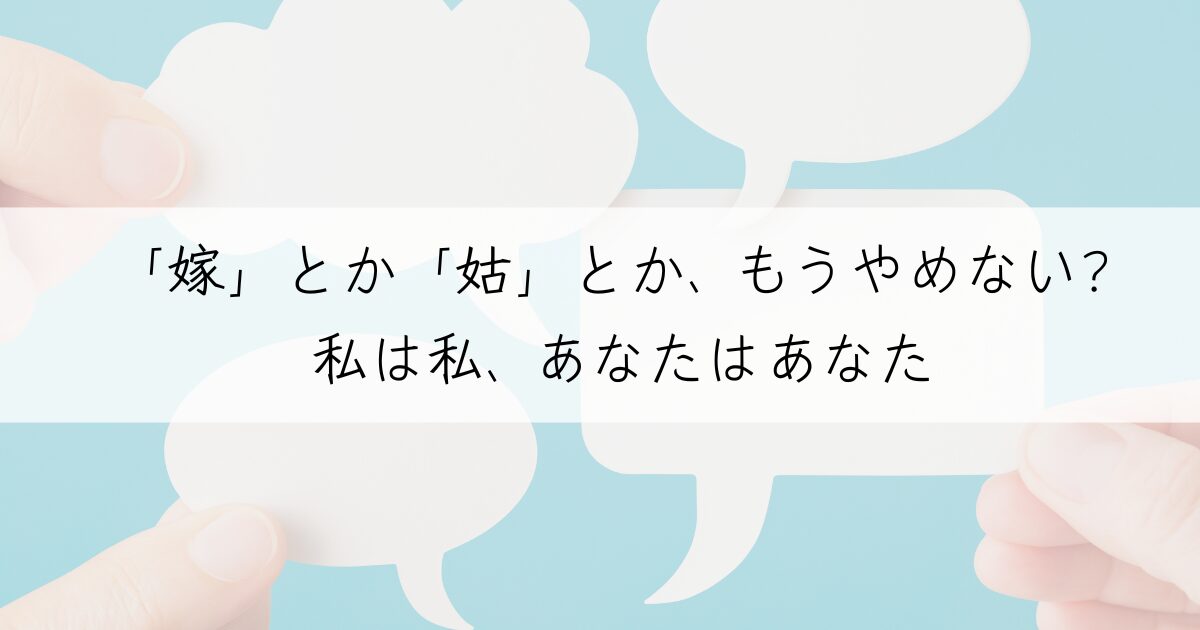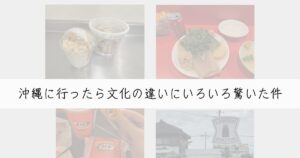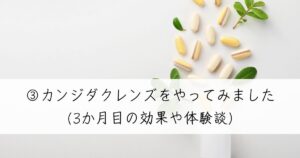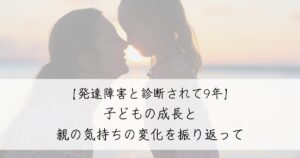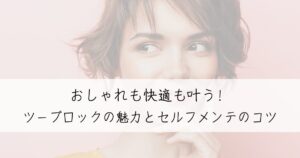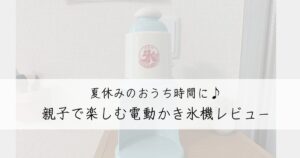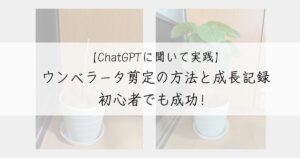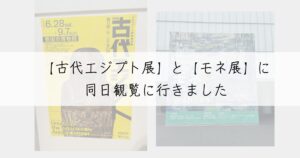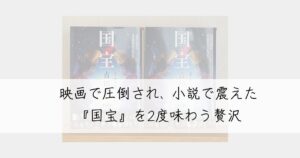やまだ
やまだ名前で呼び合える関係が心地いい。
私は結婚して「妻」になった。
けれど「〇〇の嫁」といわれるとどうしてもしっくりこない。
女に家と書いて『嫁』、女に古いと書いて『姑』。
その呼び名はもう、今の世の中には合わないと思うのです。
今回は「結婚後の女性の呼び方について」考えてみたいと思います。
結婚後の女性の役割、いろいろ自由になりたい人はぜひ最後までご覧ください。
役割じゃなく、名前でつながる関係へ
「嫁」という言葉が持つイメージ

女に家と書いて『嫁』と書く。
「〇〇のお嫁さんだよ」
と結婚後に言われることは、今でも普通です。
しかし、この「嫁」という呼び方が
結婚した相手の家の従属物
みたいな印象を受けて、私はものすごくモヤモヤします。
「嫁入り」「嫁ぐ」「嫁の務め」——
どれも、“家”に入る人、従う人、仕える人という意味が強いんですよね。
現にSNSでは「〇〇家の嫁として~」「長男の嫁なら〇〇して当然」という価値観が垣間見える投稿が多々あり、
我慢して義実家にいく私をほめてください
という妻側の自虐コメントがずらっと並びます。
嫁は奴隷じゃないし、夫の親戚側の部下でもないのに。
「姑」は女性のラスボス?

女に古いと書いて『姑』。
「姑(しゅうとめ)」という響きもまた、どこかで“怖い・支配的”という印象を与えます。
家を取り仕切る女性が古いの??
しかも「女が古い」ってひどく女性のことを蔑むイメージです。
「女性は若い方がいい」「40歳すぎたらみなおばさん」
こんな呪いがいまでも平気である世の中って、正直どうかしてるとすら感じます。
「嫁(よめ)」の語源と漢字の意味を調べてみたら

「嫁と姑っていつからこの呼び名なのか」を調べてみたら、次のようなことが分かりました。
「嫁」について、
- 元々は「他家にとついだ女性」という意味で、「結婚して夫の家に入る女性」を表している
- 古代中国の制度(家父長制)に由来しており、「家に“入る”女」というニュアンスが強い言葉
つまり、嫁は「家のものになる女」とされてきたという、非常に家制度的・男性優位の思想が反映された言葉なのだそうです。
「姑」の語源と漢字の意味
「姑」について、
- これは「年上の女性」という意味が元々あり、義母や実母などを指す言葉
- 時代が進むにつれて「夫の母(義母)」=「姑」という意味で使われるようになった
ここでの「古」は「年長者」「先に生まれた人」を示しますが、現代の感覚で見れば「古い女」というふうに見えるので、
 やまだ
やまだ人生の先輩をディスってんのか!!
静かに怒りが湧いてきます…。
いつからこの呼び方?
「嫁」や「姑」という言葉は、奈良〜平安時代には既に日本語として使われていたそうで、
日本での家父長制が制度化された江戸時代以降、「嫁=家に仕える存在」という色合いがより強くなり、呼称としても定着していったとのこと。
これらの言葉は、漢字に込められた背景があまりに時代錯誤で、現代の「個人を尊重する関係性」にはなじみにくくなっていると感じます。
「いい嫁の呪い」で苦しかった過去

結婚して「嫁」の立場になった時、脈々と受け継がれてきた「いい嫁」のイメージが、静かに私を苦しめていきました。
誰にもそうしなさいと言われていないのに、
長期休みは義実家連泊、帰省時のお土産の用意から、お中元お歳暮母の日父の日誕生日のプレゼントの用意、年賀状の手配や印刷、夫親戚側の連絡係など
自らやってきました。
でも40歳を機に年賀状終いをしたときに、夫に
これからはもう年賀状の用意も印刷もしないから自分でやってね
といった時に夫は、
「わかった~」とあっさり了承。
それを見て、
 やまだ
やまだあれ?別にやらなくてもよかったのかな…?
と思ったんですね。
別に私が先回りしたり、やりとりしなくても実は何も問題はなかったのかも、と。
その気づきから少しずつ自分の中にある「嫁として」を手放し、嫁とは言わず「妻」というようになりました。
言葉って、想像以上に力がある

先の「嫁」「姑」の語源のように、言葉が関係をつくり、社会的役割が自然と(嫌でも)与えられるようになります。
だからこそ見直したい。
「嫁」や「姑」という言い方ではなく、対等な関係として伝わるような言葉を選んでいきたいと思うのです。
役割じゃなく、名前でつながる関係はどうでしょうか。
たとえば、
「嫁」→「◯◯(自分の名前)さん」
「姑」→「◯◯(義母の名前)さん」
他人に説明するときは「夫の母」「夫の実家」「妻」「パートナー」「相方」など。
最初はぎこちなくても、“名前で呼び合う”って、自分を取り戻す第一歩だと感じます。
名前で呼ぶようになってどうなった?

私は数年前から、夫両親をそれぞれ名前で呼ぶようにしています。
それまで「おとうさん」「おかあさん」だったのですが、名前で呼ぶようなってから「一人の人」としていい距離感で今まで以上にいいお付き合いができるようになりました。
実際、夫の母はとても優しく俗にいう嫁いびりみたいなことは一切なかったのに、
私の中にある「いい嫁像」がフィルターをかけて「上司と部下」といった関係を作っていた気がします。
もうこんな価値観要らないし、子供たちにも渡したくないです。
今は、私自身の人生を生きたい。
嫁じゃなく、“山田明日美”として、自分の好きな人と好きな関係を築いていきたい。
心からそう願います。
おわりに
いかがでしたか?
今回は「「嫁」とか「姑」とか、もうやめない?私は私、あなたはあなた」についてお届けしました。
 さくらさん
さくらさん女性が縛られる価値観はなくしていきたいですね
 やまだ
やまだどっちが上とかないのが当たり前の世の中に。
「嫁」って言葉に心がギュッと縮こまるなら、その肩書き、もう脱いでしまいましょう。
〇〇の嫁ではなく、戸籍上「妻」なだけ。
嫁と言わなくても家を追い出されたりしないし、社会的地位を失う世の中じゃありません。
言葉が持つエネルギーは大きいので「名前で呼ぶこと」、試してみてください。
この記事が10年後「日本て結婚すると色々生きづらい時代もまだあったんだね」と笑って言えることを願っています。
それではまた♪
リラックスタイムにおすすめ