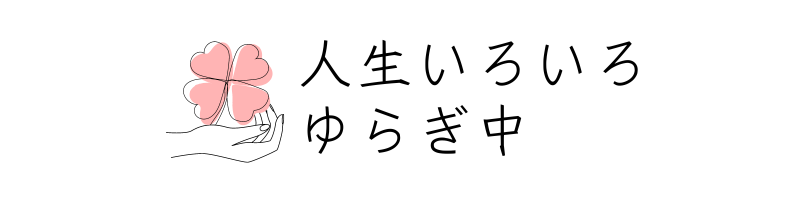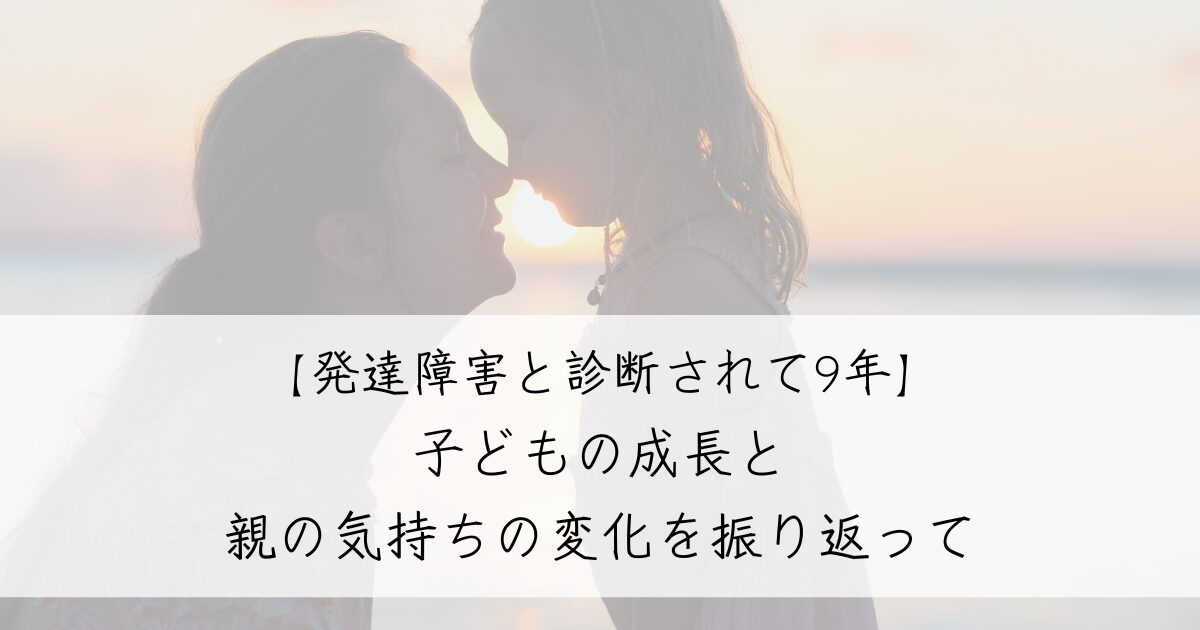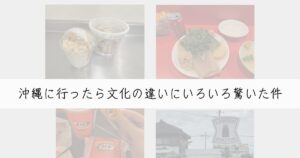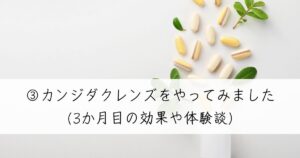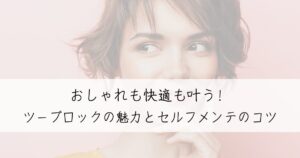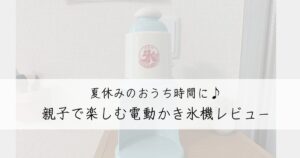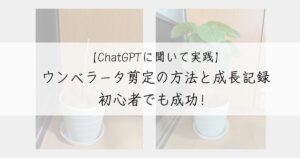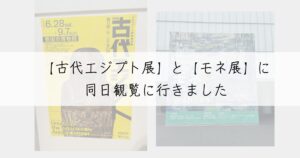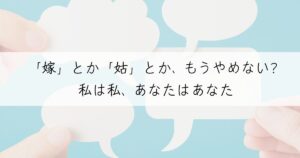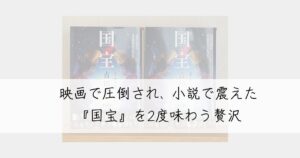やまだ
やまだ親子で今も精進中です
下の子が3歳の時に言葉の遅れから、発達障がいがわかりました。
そこから数年は、自分にとって「人生を初期化する」レベルでの大きな変化が起こりました。
子供がきっかけで私は起業し、今に至るのですが、診断されて9年目の今思うことを以前を振り返りながら今回記したいと思います。
同じように「子供が発達障がいかもしれない…?」「今の状況が先が見えずつらい」など感じている方の参考になりましたら幸いです。
ぜひ最後までご覧ください。
適切な支援と相談できる場所があることは親子の成長につながる
2022年に子育てコラムを書くことになりました
まずはこちらをご覧ください。

2022年にベビモウェブ様で、5回にわたってコラムを連載させていただきました。
きっかけは、生活情報サイトで片付けのプロとしてコラムを掲載いただいていた時の担当者さんが、ベビモウェブに移動された際に私がメールで子供のことを書いていたことでした。
「お子さんが発達障がいと診断されて、親の気持ちやサポート、どんな経緯をたどったのか書いてくださいませんか」と依頼が来たのです。
この時点で、診断がついてから6年が経っていて、私自身もいろんな変化を感じ落ち着いていた頃でした。
でも、当時の記憶もあまりなく、ただつらかったあの頃の気持ちを振り返るのは正直気が進まなかったです。
悩む中でふと、
今だから書けること、言えることがある
そんな自分の声が聞こえてきたんです。
そこから、コラムの着地点が全く未定のままお引き受けすることになりました。
泣きながら書いて、その過程で当時の自分をいたわる時間を過ごした気がします。
連載されたのが、2022年9月のこと。
読んでくださった方から、沢山の反響をいただきました。
受けてきた療育の記録
子供の特性としてあったのは「言葉の遅れ」「認知機能の弱さ」でした。
コラム掲載時点で、子供は小学校3年生。
現在、小学校6年生になりました(早い!)。
思い出せる限り、息子が受けてきた療育を時系列で並べていきたいと思います。
- 入園前
-
親子で療育施設に週2で通う
言語療法も入園前に開始
- 保育園時代
-
加配枠での園生活
言語療法継続
発達外来に半年に1度通院し、運動療法も取り入れる
- 小学校
週1回の通級を行う
放課後等デイサービス(放デイ)2つに通う
(途中)通級を担当教諭と相談し終了
(小4)放課後等デイサービス1つを終了し、個別対応に特化した放デイを追加
(小5)小1~お世話になっていた小規模集団の放デイを終了、個別対応の放デイも終了
(小6)療育なく過ごす
現時点で療育は終了し、「一般的な小学生男子」として成長しています。
療育を受けてどうだったか

診断時はとにかくこの現実を受け入れることが難しく、今でも胸が苦しくなりますが、入園前に親子で療育施設につながったことは間違いなく、
相談できる場所があったことで親子ともに救われた
と断言できます。
もしあのまま私が受け入れることができず、世間一般の「普通」にとらわれて適切な支援を子供にできていなければ、きっと子供は周りとうまくなじめず、私も孤独に陥っていただろうと思うからです。
様々な支援があること、同じように悩む親御さんとの共有、療育のプロの先生方のフォローを受けられたこと
私にとって、ただただ絶望でしかなかったことに、少しずつ光がさして、進む道がみえてきたことで、
自分の中の悲しみを自分で受け入れることができ「できることをやっていこう」と思える機会になりました。
よく聞いていた曲
子供が保育園時代に、よく聞いていた曲が2つあります。
YUKI「歓びの種」
1つ目は、YUKIさんの「歓びの種」。
「見逃してしまう 歓びの種を 暖かい大地で育てましょう」
「与えられたのなら 受け止めよう 見逃してしまう 歓びの種を 暖かい大地で育てましょう」
私には見えていない、子供の成長や素晴らしいところがあるんじゃないかな
そんな風に感じて、優しく背中をさすってもらえるような忘れられない一曲です。
実際この曲は、YUKIさんのお子さんをSIDSでなくされた後に作られたそうで、考えたら涙が本当止まらない曲です。
半崎美子「明日へ向かう人」
子どものことを話すと、時々相手からの発言に「うっ…」となることがありました。
励ましやアドバイスが、尖ったナイフのようにざくざくと刺してくるような、そんな風に受け止めてしまう時が長く続いたんですね。
そんな時に、
「声を枯らして泣いても 辿り着けない場所がある
それでも信じることを生きることを あきらめないで」
という歌詞に泣けて泣けて…。
変わらないこと、望んでもどうにもならないこと、そんなことがあることを、時間をかけてゆっくり受け入れることができるようになったのも、この曲のおかげだと思っています。
今も聞いては励まされ、癒されています。
普通ってなんなんだろう

コラムの最後に書いているのですが、
「普通」って何なの?
ということです。
周りと比べて、遅れていたり、尖っていたり、学力が低かったり「周りと違うこと」は、悪なんでしょうか。
私は一生懸命勉強して、子育てをしていたけれど、いつもどこかに自信がなく過ごしてきました。
基準が「周りと比べての自分」だったから。
でも、子供のことがきっかけで、
見えているものがすべてではない
という気づきを得ました。
人がうらやむ人生を送っていても、順風満々に見えても、定型の成長でも、
誰しも凹凸がある。私だってそう。
周りと比べて恐れて落ち込むのではなく、今の子供を見よう。
いい悪いのジャッジではなく、生きていることに感謝しよう。
困っていたら助けてくださいと言おう。
子どもが私に教えてくれたことは、私の人生を豊かに変えてくれるものだったのだと今は感じています。
子育ては続きます。
いつか親元を子供が巣立つとき、いってらっしゃいと背中を押せるようにありたいです。
おわりに
いかがでしたか?
今回は「発達障がいと診断9年後の子どもの成長と親の気持ちの変化を振り返って」についてお伝えしました。
 さくらさん
さくらさんいろんな支援があって葛藤もたくさんあったんですね
 やまだ
やまだ人生に深みが増した気がします…
9年間を振り返って感じるのは、「一人で抱え込まなくていい」ということです。
発達障害と診断されても、子どもは変わらず大切な存在であり、私たち親もまた成長していける。
もし今、不安でいっぱいの方がいたら、どうか一人で悩まないでほしいです。
そして今「受け入れらない」としても、それを責めないでください。
自分の心だけは、いつだって味方でいてほしいと思います。
この記事が、先が見えずにつらい思いをされている方の肩の力がふっとラクになるきっかけになりましたら心から嬉しいです。
それではまた。
コラムはこちらから